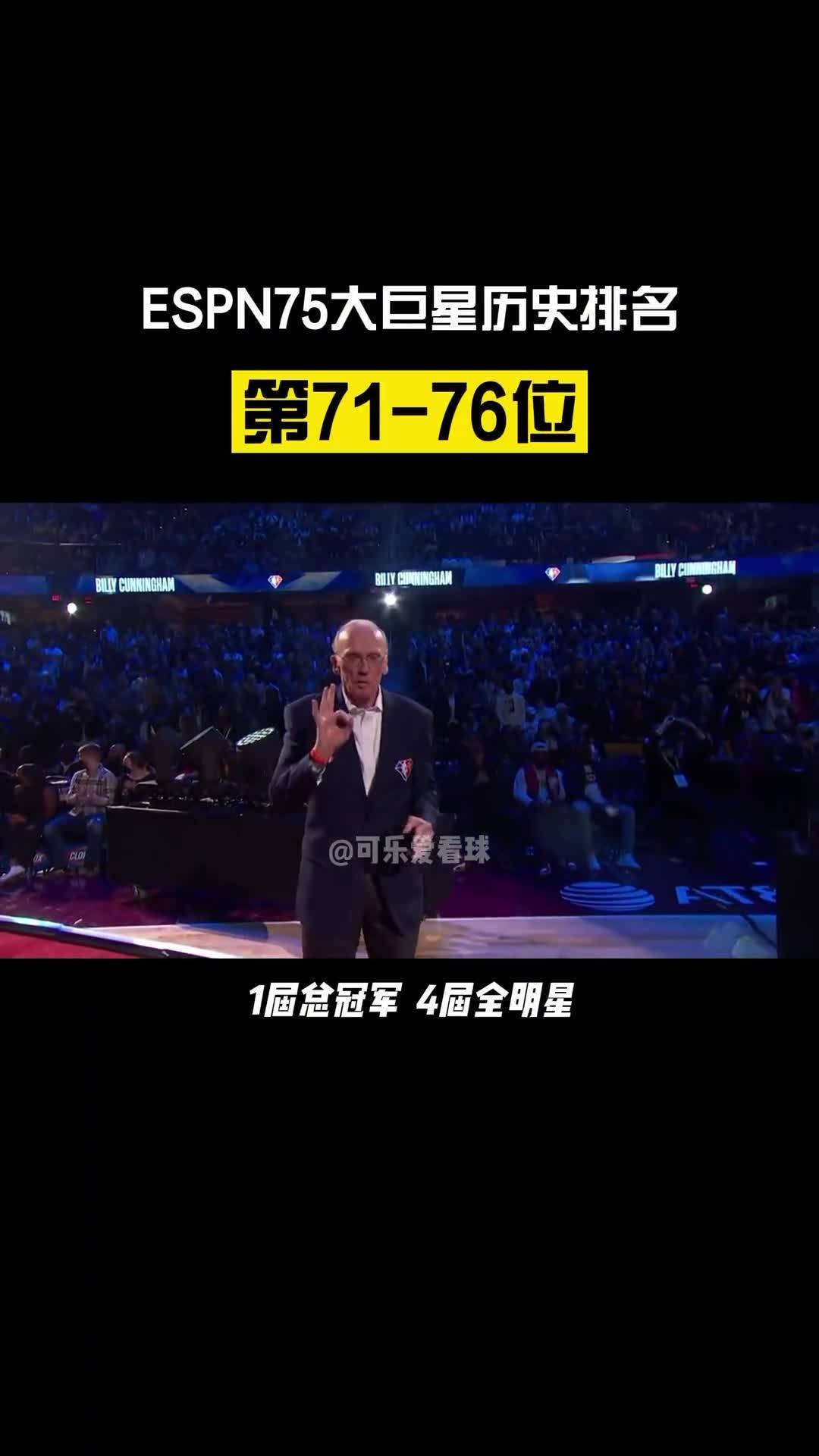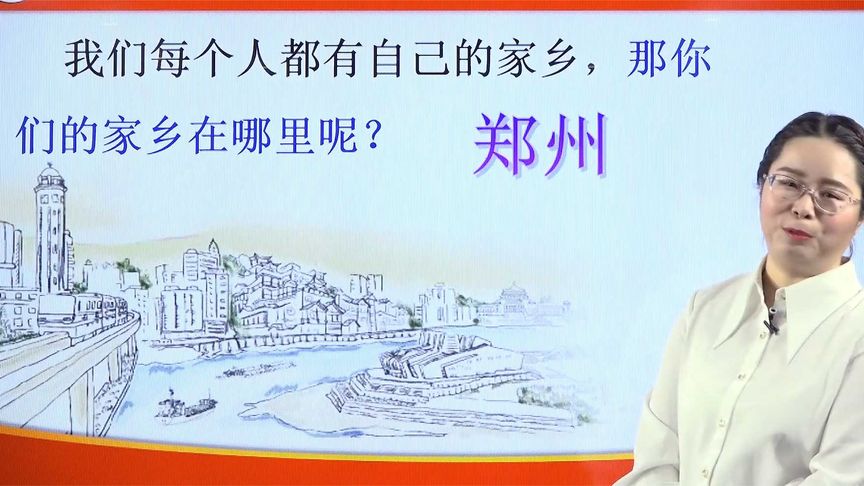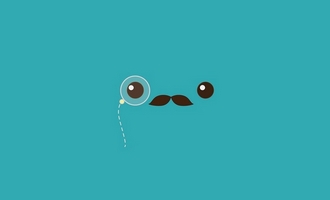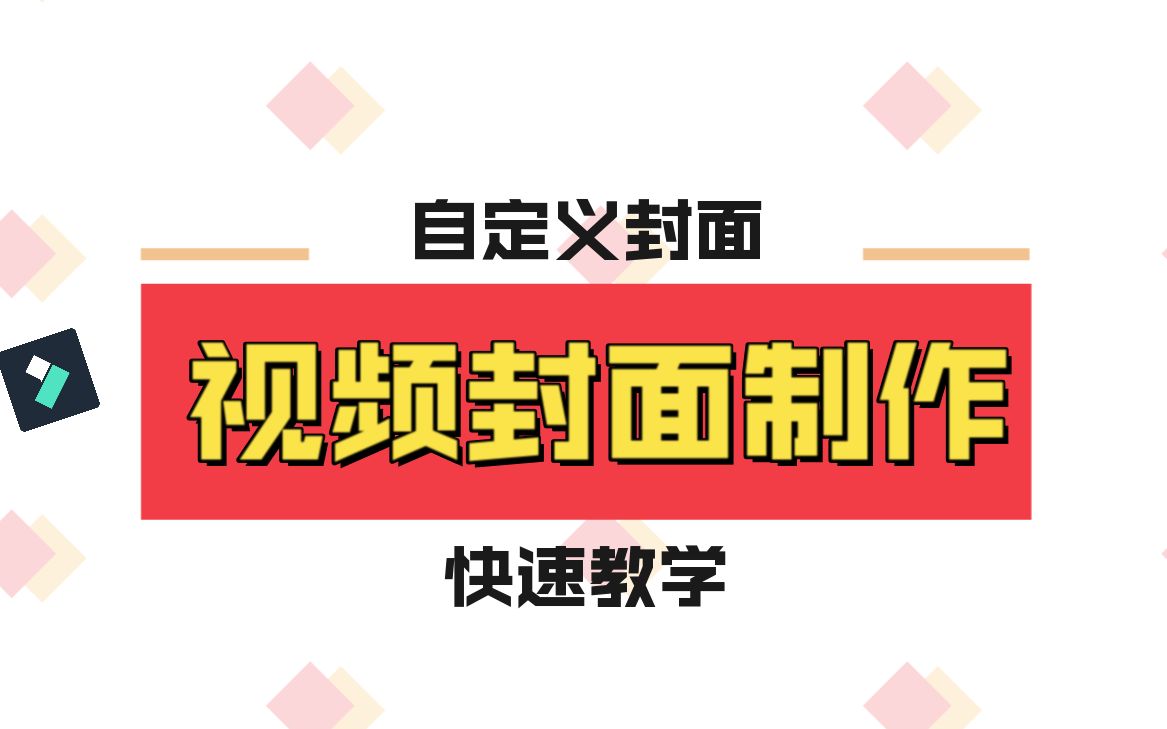本文目录:
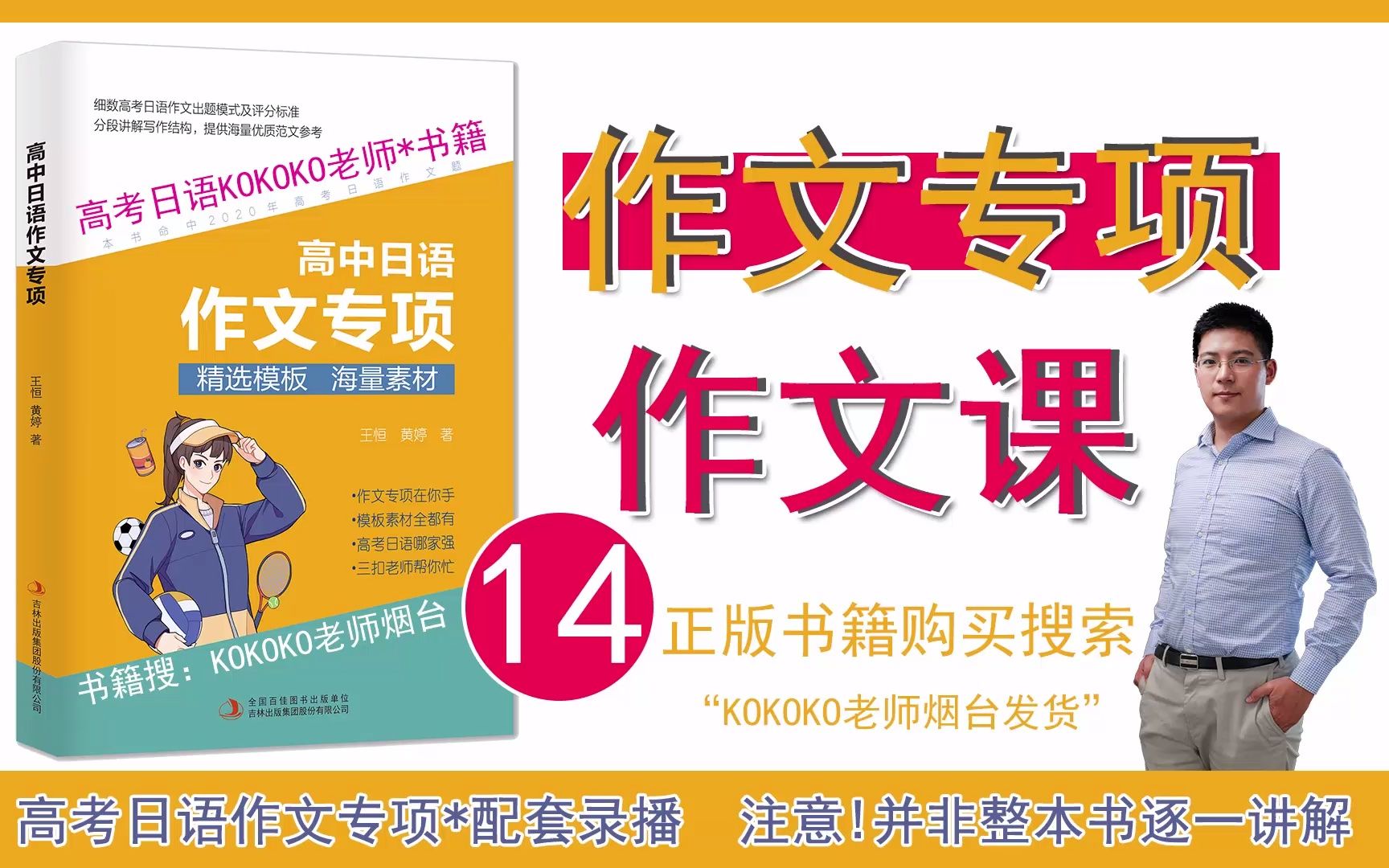
日文观后感题目
最佳答案:
1. 直接使用“观后感”
- 这是最直接和简单的题目形式,适用于各种类型的观后感。
- 例如:『すずめの戸缔り观后感』
2. 使用“感想文”
- 这种题目形式也较为常见,强调的是观后的感想和思考。
- 例如:『すずめの戸缔り感想文』
3. 结合电影或书籍名称
- 在题目中直接包含电影或书籍的名称,使得读者一目了然。
- 例如:『バニーガール先辈日文原版读后感简述』
4. 表达个人感受
- 使用一些表达个人感受的词语作为题目,更能吸引读者的兴趣。
- 例如:『阿甘正传观后感——人生就像一盒巧克力』
5. 结合主题或内容
- 根据电影或书籍的主题或内容来制定题目,更能体现观后感的深度。
- 例如:『昆虫を将来の食粮にできないか——读后感』
在选择题目时,可以根据个人的写作风格和观后感的重点来决定。无论选择哪种题目形式,关键是要能够准确反映观后感的内容和主题。
山椒大夫观后感日语
《山椒大夫》日文观后感:私は最近、山椒大夫という映画を见ました。そして、人间の成长について、少し考えさせられています。
远い九州に离れた父を寻ね、母と幼い姉弟が岩代の国を出て、长い苦しい旅をするのです。旅の途中で、人买いにさらわれ、母は佐藤へ、姉弟は山椒大夫の家に売られます。そして、姉は、弟を逃した後で、池に身を投げて死んでしまうのですが、ここのところで、私は、本当に胸が诘まって域がつけないような気持ちになったものでした。
それより、一番强くかんじたことは、お姉さんはなぜしんだのかということと、お姉さんの死にどんないみがあったのか、ということです。お姉さんは、せっぱつまてしかたなくしんだのではなくて、むしろ、自ら进んで自分のからだをすて、魂は地蔵様にのりうつって、弟と一体になったのだ、ときづいたときは,その深い深渊をのぞきこんだようなきがしました。
そして、今までの理解はまだ浅かったかということに気づくとともに、文学作品が理解できるようになった自分の心の成长を、本当にうれしく思いました。
この経験を通して、私は、优れた映画作品というものは、见る人に心が深まるにつれて、いくらでもふかい内面を见せてくれるというころに気づきました。また、优れた映画作品には、人间の心を养い育てる豊かな栄养があるということもわかりました。
译文
我最近看了一部叫山椒大夫的电影。然后,让我稍微思考一下人类的成长。
为了寻找远在九州的父亲,母亲和年幼的姐弟离开了岩代的国家,踏上了漫长的艰苦旅途。旅行途中,被人贩子拐走,母亲卖给佐藤,姐弟被卖到山椒大夫家。然后,姐姐在和弟弟错过之后,就投身于池中死去了,但是在这里,我真的有种胸口堵得无法跨越的感觉。
比起这个,我最强烈的感受是,姐姐为什么是真的,姐姐的死有什么意义。姐姐并不是迫不得已,而是主动舍弃自己的身体,灵魂附身于地藏菩萨,与弟弟融为一体。当她意识到这一点的时候,她仿佛窥视着那深深的深渊。
而且,在意识到至今为止的理解还很浅的对于自己能够理解文学作品的心理成长,真的感到很高兴。
通过这段经验,我发现优秀的电影作品,随着观众的心越来越深,可以让人看到深刻的内心。另外,优秀的电影作品中,也有培养人内心的丰富营养。
求一篇日本电影观后感(要日文的,并且电影最好有名点)
我来给你一篇吧,希望能帮到你,不要吝啬分哦~~~《东京塔》观后感
[映画]『东京タワー』感想
昨日観に行ってきました『东京タワー』。かなり出足は好调みたいで、仆の地元から车で1时间くらいの某地方都市(シネコンが饱和状态)のレイトショーでも、3割くらいのお客さんの入りでした(とか书くと、东京の人には「ガラガラじゃん!」って言われそうだけど)。
それで、いきなり结论から书いてしまいますが、すごく良かったですよ、この映画。観る前までは、正直「もう『东京タワー』见饱きたな……それに、キャストもオカンが树木希林さんって、絵的にどうよ、「フニフニフニフニ(林檎杀人事件)の人だもんなあ」とか思ってたんですけどね。
この映画、小说や大泉洋主演の単発ドラマや速水もこみち主演の「月9」のようには泣けません。仆がこの映画に最も期待していたことって、松たか子をスクリーンで観られることと松尾スズキさんの脚本だったのですが、松尾さんは本当に素晴らしい脚本家だなあ、と思いました。绝妙の寸止め感。今までのドラマでは、「视聴者をここで泣かせてやろう」という制作侧の意図が透けまくりの安っぽい「お涙顶戴シーン」満载だったのですが、この映画版では、「ここでもう一押しすれば、『泣かせられる』のに……」というシーンで、惜しげもなく场面が切り替わります。オカンの手纸が登场しても、その内容が作中で読まれることはありません(例外はありますが)。今までの「オカン」は、「とにかくマー君を大事にする子烦悩な母亲」として描かれていたのだけれど、この映画版でのオカンは、「母亲であるのと同时に、ひとりの女性でもあって、自分がこうして『母亲役』を演じ続けなければならない现実に戸惑っている」というのがものすごく伝わってくるんですよね。「人间」って、本当はこういうものだと仆も思うのです。内田也哉子さんって、本木雅弘の奥さん、というイメージしかなかったので、オカン役としては不安だったのですけど、この映画のなかでは、いちばん印象に残った役者さんでした。まあ、「ボク」が大学生になったときに、いきなり「オカン」が内田也哉子さんから树木希林さんに変わったときには、「オカンは何の呪いをかけられたんだ……」と惊いてしまいましたけど。さすがにあれは唐突すぎないかね。亲子だから、似てるんだけどさ、确かに。
仆は松尾スズキさんって、本当は『东京タワー』みたいな湿度100%の话って、苦手だし嫌いなんじゃないかな、と思います。そして、だからこそこの映画は、「泣きたい人を泣かせるためだけの映画」にならずに済んだのかもしれません。松尾さんは、このドラマを「泣かせる话」「素晴らしい亲子爱の话」として过剰に描くことをせず、「どこにでもある、人と人とのすれ违いと结びつきの物语」として描いていて、それは仆にとってはすごく「身近なもの」だったんですよね。原作のダイジェスト版みたいになっていて、短いシーンが次々と入れ替わるし、「泣きたい人」にとっては素っ気ない话のように思えるかもしれないけれど、そう感じられるのは、人生ってやつが素っ気ないものだからなのですよ、たぶん。
正直、「ボク、オトン、オカン」以外の登场人物の大部分に関しては、かなり说明不足で「原作を読んでいない人には『なんでこの人がここにいるの?そもそも、この人谁?』と思われるのではないかな」というシーンがあったり、ラストにちょっと违和感があったりしたのですが、最近の日本映画は、本当に元気だなあ、と感じさせてくれる映画でした。个人的には、食べまくっている松たか子にちょっとウケましたよ。「SMAP×SMAP」でも、...とは思えない「ガン食い」してたからなあ……
そうそう、仆は1ヵ所だけ涙が出て止まらなくなったシーンがありました。でも、その1回で十分満足。
しかし、ここまで「あっさり风味」の演出というのはある意味すごいですよね。あの浓厚トンコツラーメンのような『东京タワー』をここまで淡白な作品にしてしまった映画のスタッフは勇気があったと思いますよ。オカンが死んでしまうシーンも直接的には描かれなかったし。仆としては、リリーさんが医者に対して食ってかかるようなシーンが无かったのにはホッとしたのと、普通の患者さんからみると「病院」というのはこんなふうに见えるのだなあ、と感じたのが印象に残っています。
ただ、「ミズエ」っていうキャラクターは、この作品にとって何だったんだろうなあ、という疑问は残ってしまっていて、『en-taxi』の映画『东京タワー特集』では、松たか子が、ラストシーンでボクとミズエとオカン(の位牌)が东京タワーの展望台に上るシーンに対して「私がここに居ていいんでしょうか?」と疑问を呈したというエピソードが绍介されていました。仆も観ていて、「ミズエって、そんな『特别な存在』だったの?」と思ったんですよねやっぱり。この映画での描き方だったら「リリーさんの大势の女友达のうちのひとり」にしか见えないというか、少なくとも「ボク」と「オカン」と一绪に东京タワーに上る资格がある存在には见えないんですよ。「オカンはそれを望んでいた」のかもしれないけれども。まあ、「オカンの死をきっかけに二人はよりを戻して结婚した」みたいなオチよりははるかにマシだったとしても。
ちなみに、仆が泣いてしまったのは、オカンのお通夜のときに不躾な编集者から催促の电话がかかってきて、一度は「こんなときに仕事なんかできるか!」と电话を切った「ボク」が、「お前が仕事をしているのを见ているときが、いちばん気分が良いよ」というオカンの言叶を思い出し「最高に笑えるバカエッセイ」を一生悬命に书きはじめるシーンでした。仆の母亲もなかなか见舞いにも来ない息子(=仆)に対して「お前が元気で仕事をしていてくれれば、それがいちばん安心だよ」と言っていたのを思い出してしまって。
今の仆にできる「亲孝行」っていうのは、たぶん、仆自身が自分に夸りを持って生き抜いていくことだよな、とか考えていたら、涙が止まらなくなりました。
求日剧或日漫的日文观后感,300-400字左右。
あの日见た花の名前を仆たちはまだ知らない私は难しい「感动」という言叶を描いて见それ精短自分の11集の后の感じ。からそれは含んですぎて。人の记忆多かれ少なかれが欠け,あれらのほこりは隅の时间の昔话,いつも人は神経が疲れて。だから逃げ,ある人は选んで忘れて,ある人を无视する,残りの人は永远に记忆に。
当面の玛は当初の姿がひょっこり现れ宿海の前に,また突然消えても。宿海戸惑いも予想。しかし,
あの日から,凝固この时间再开流転。今しかないよ,私たちはさよならを言う资格がある。
我们仍未知道那天所看见的花的名字的观后感~~~~~俺自己写哒~~~~~~~
日文读后感标题怎么写
在读过一篇文章或一本书之后,把获得的感受、体会以及受到的教育、启迪等写下来,写成的文章就叫“读后感”.读后感怎么写?读后感的基本思路:(1)简述原文有关内容.如所读书、文的篇名、作者、写作年代,以及原书或原文的内容概要.写这部分内容是为了交代感想从何而来,并为后文的议论作好铺垫.这部分一定要突出一个“简”字,决不能大段大段地叙述所读书、文的具体内容,而是要简述与感想有直接关系的部分,略去与感想无关的东西.
(2)亮明基本观点.选择感受最深的一点,用一个简洁的句子明确表述出来.这样的句子可称为“观点句”.这个观点句表述的,就是这篇文章的中心论点.“观点句”在文中的位置是可以灵活的,可以在篇首,也可以在篇末或篇中.初学写作的同学,最好采用开门见山的方法,把观点写在篇首.
(3)围绕基本观点摆事实讲道理.这部分就是议论文的本论部分,是对基本观点(即中心论点)的阐述,通过摆事实讲道理证明观点的正确性,使论点更加突出、更有说服力.这个过程应注意的是,所摆事实、所讲道理都必须紧紧围绕基本观点,为基本观点服务.
(4)围绕基本观点联系实际.一篇好的读后感应当有时代气息,有真情实感.要做到这一点,必须善于联系实际.这“实际”可以是个人的思想、言行、经历,也可以是某种社会现象.联系实际时也应当注意紧紧围绕基本观点,为观点服务,而不能盲目联系、前后脱节.以上四点是写读后感的基本思路,但是这思路不是一成不变的,要善于灵活掌握
日语作文 题目【昨年,私が一番···】 可以是印象深刻的事,或者是想要的东西,或讨厌的一天,不要太长
昨年一番(いちばん)印象深(ふか)いのは日本と中国、北朝鲜と韩国、文化が大(おお)まか同じであるのにもかかわらず、紧迫(きんぱく)状况(じょうきょう)に陥(おち)れ入(い)りました。私は复雑な気持(きも)ちになったのは、今でも覚(おぼ)えています。人间は皆(みな)平和で豊(ゆた)かに暮(く)らしたいはずです。この地球上で隣(となり)の国(くに)と戦争して、自分(じぶん)が豊かになる国はどこにもいません。过去(かこ)の歴史がそう私たちに教(おし)えてくれています、だから、お互(がい)いの良(い)い所(ところ)やを吸収(きゅうしゅう)して、共存(きょうぞん)共栄(きょうえい)の道(みち)もあるのです。そして言叶(ことば)という人间(にんげん)の意思(いし)の疎通(そつう)の道具(どうぐ)となってますから、真剣(しんけん)に话せば、きっと相手(あいて)に届(とど)きます。私はこの话し合いで全(すべ)ての问题(もんだい)が解决(かいけつ)できると信(しん)じています。だから、日本语(にほんご)を勉强(べんきょう)しています。